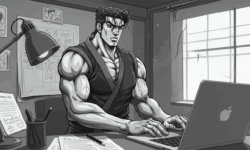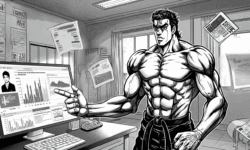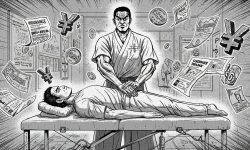接骨院の開業において、立地選びは開業の成功を左右する最重要ポイントです。家賃の高さや人通りの多さだけで判断すると、思わぬ失敗につながることもあります。この記事では、ターゲット層に合ったエリア選びの考え方や成功・失敗事例、チェックリスト、法的な注意点までを紹介しています。
▼関連記事▼
・接骨院で保険を活用する方法と注意点:治療費の適正な取り扱いと実践的ガイド
・接骨院開業に役立つブログの活用法とは?集客・経営に効く情報発信のポイント
目次
立地選びが接骨院開業の成功を左右する理由
開業後すぐの集客は「立地の良し悪し」で決まる
接骨院の開業後に最初の集客を成功させるには、立地が極めて重要です。駅近や大通り沿いなど人通りの多い場所は、視認性が高く自然な集客が期待できます。一方、住宅街の奥まった場所やアクセスの悪いエリアでは、開業当初から集客に苦戦するケースが多く見られます。立地の良し悪しは、認知度の差に直結する大切な要素と言えるでしょう。
訴求できる層(ターゲット)と立地の相性
自院がターゲットとする患者さんの層と立地との相性も重要です。例えば、学生やスポーツ選手をターゲットにするなら学校やスポーツ施設の近く、高齢者を対象にするなら住宅地や団地の近くが適しています。地域の人口構成や年齢層、周辺施設を事前にリサーチすることで、集客効率を高めることが可能です。
家賃・固定費の影響
一等地の物件は集客面で優位な反面、家賃や固定費が高くなりがちです。収益が安定するまではランニングコストの重さが経営を圧迫するため、コストと見込み集客数のバランスを見極めることが重要です。収支シミュレーションを行い、利益が見込める立地かどうかを数値で判断しましょう。
開業を成功させるためのチェックリスト
立地選びの3つの基本ステップ
接骨院の開業を成功させるには、立地選びが欠かせません。感覚や勘だけで決めるのではなく、明確なステップを踏むことで、集客力の高い場所を選定できます。ここでは、失敗しないための立地選びの3つの基本ステップをご紹介します。
ターゲット層の明確化
まずは、「どんな患者さんに来てもらいたいか」を明確にしましょう。ターゲット層を定めることで、立地の条件や訴求方法が大きく変わります。ターゲットの生活動線やニーズに合ったエリアを選ぶことが、集客とリピート率アップの第一歩です。
- 高齢者層:住宅街・団地・バス通り沿いなど、徒歩やバスで通えるエリア
- ファミリー層:スーパーや公園、保育園・小学校に近い場所
- 学生層:高校や大学、スポーツクラブの周辺
- ビジネスマン層:駅近・オフィス街・夕方以降に通いやすい立地
エリアの候補出し
ターゲットが明確になったら、次に行うのは具体的なエリアの候補出しです。候補エリアは、「人が集まりやすいか」「利便性が高いか」を基準にしましょう。
例:
- 通勤・通学動線上:駅と自宅の中間にある商店街やバス通り
- スーパーの近く:買い物ついでの来院を見込める
- 学校や幼稚園の周辺:保護者の来院や子どものケガ対応に最適
- 病院やクリニックの近く:相乗効果を狙える
候補地の調査と比較
候補エリアが絞れたら、最後に現地での調査と比較を行います。以下の項目を基に、複数の候補を比較検討しましょう。データだけでなく、実際の時間帯ごとの人通りや周辺施設の利用状況も確認することで、現実に即した判断ができます。
例:
- 通行量(徒歩・自転車・車):人の流れがあるか
- 視認性:通行人がすぐ目にする場所にあるか
- 駐車場の有無:車利用の患者さんが多い地域なら必須
- 競合院の数と評判:競合が多すぎないか/逆に集客が集中する場所か
立地タイプ別|メリット・デメリット比較
接骨院を開業する際、「どの立地タイプを選ぶか」はその後の集客・売上に直結します。ここでは、代表的な立地タイプ3つの特徴をメリット・デメリットに分けて解説します。自院のターゲットや経営方針に合った立地を選ぶための判断材料としてご活用ください。
駅前エリア
▶ こんな方におすすめ:短期間で集客したい、差別化戦略が明確な方
メリット
- 通行量が多く、自然な集客が見込める
- 駅を利用する会社員や学生をターゲットにできる
- 目立つ立地のため、認知が早い
デメリット
- 家賃や保証金が高額になる傾向
- 接骨院や整体などの競合が多く、差別化が必要
- 駐車場の確保が難しい場合がある
住宅街エリア
▶ こんな方におすすめ:地域密着型で長期的な安定経営を目指す方
メリット
- 地元の住民(高齢者・主婦・ファミリー層)にアプローチしやすい
- 家賃が比較的安く、ランニングコストを抑えられる
- リピーターがつきやすく、安定した経営が可能
デメリット
- 認知されるまでに時間がかかる
- 通行量が少ないエリアでは、外看板や地域広告が必要
- 集客スピードにやや難あり
オフィス街エリア
▶ こんな方におすすめ:平日昼間の来院ニーズに対応できる施術スタイルや営業時間を設けられる方
メリット
- 平日昼間の集客力が高い(会社員・デスクワーカーの肩こり・腰痛対策など)
- 昼休みや退勤後に通いやすい立地
- 即効性のある施術が好まれ、単価アップも可能
デメリット
- 土日・祝日は来院数が激減する可能性
- 周辺企業のテレワーク化で需要が減ることも
- オフィス移転などの外的要因に左右されやすい
エリアごとの注意点もチェック
- 例えば、新宿・渋谷など都心部の駅前エリアは通行量は非常に多いものの、競合が多く家賃も高騰しているため、ブランディング力が問われます。
- 一方郊外の住宅地(例:千葉県・埼玉県の駅徒歩15分圏)では、地元コミュニティとの連携や紹介ルートの構築が鍵になります。
- また、郊外モール周辺やバス通り沿いなども狙い目ですが、駐車場の有無や交通量の把握も重要になります。
成功・失敗事例から学ぶ立地選び
立地選びは、接骨院経営における「最初の勝負どころ」です。実際に、立地の選定によって成功した院もあれば、集客や経営に苦戦した院も存在します。下記では、実例をもとに立地選びのポイントをご紹介します。
成功事例|住宅街で開業し、地域密着でリピーター獲得に成功(A接骨院)
A接骨院は、駅から徒歩15分ほどの住宅街に開業。通行量は多くないものの、「地域に根ざした院」を目指し、以下の施策を徹底しました。
- 開業前から地域ポスティングや町内掲示板での周知活動
- 高齢者・主婦層向けの「午前中割」など、地域に寄り添ったメニュー展開
- リピーター促進のための紹介カードやLINE予約機能の導入
結果として、オープン半年以内にリピート率70%超を達成。住宅街という立地を活かし、「信頼」と「通いやすさ」を武器に着実に売上を伸ばしています。
失敗事例|オフィス街で開業したが、平日以外は閑散。高額な固定費で経営に苦戦(B接骨院)
B接骨院は、「人通りが多いから」という理由でオフィス街に開業。しかし、以下のような課題に直面しました。
- 平日昼間は会社員が多く来院するものの、土日祝はほぼ来院ゼロ
- ビル1階の好立地だったが、家賃と共益費が非常に高額
- リピーターが定着しにくく、新規集客に広告費がかさむ
結果、平日の売上では高額な固定費をカバーできず、1年以内に赤字化。周辺企業のテレワーク化が進んだことも影響し、想定していたビジネスモデルが崩れてしまいました。
事例からの学び|「人が多い=成功」ではない!
成功事例と失敗事例から学べるのは、ターゲットと立地の相性が何より重要だということです。どんなに人通りが多くても、自院の施術や営業時間がその地域のニーズに合っていなければ、安定経営は難しいと言えます。特に接骨院は、「地域住民に信頼されること」がリピーター獲得の鍵です。地元密着の戦略を立てられるかどうかが、立地選びにおける成否を左右するでしょう。
立地選びで注意すべき法的・行政のポイント
接骨院を開業する際、「人通り」や「家賃」だけに注目して立地を決めてしまうと、後から法的・行政的な制限に直面することがあります。開業後にトラブルを回避するためにも、立地選びの段階で以下の点を必ず確認しておきましょう。
建築用途地域の確認(店舗OKか)
土地や建物には、それぞれ「用途地域」が定められており、接骨院が営業可能かどうかは自治体のルールによって異なります。たとえば、「第一種低層住居専用地域」では、病院や接骨院などの営業に制限がある場合もあります。契約前に必ず市区町村の都市計画課などに確認し、該当地の建築基準を調べましょう。
チェックポイント
- 接骨院としての使用が認められているか
- 内装工事や用途変更に許可が必要かどうか
(出典: 国土交通省)
看板の設置制限(景観条例など)
接骨院の集客において「看板の視認性」は非常に重要ですが、地域によっては看板サイズ・設置場所・色味などに規制があります。事前に市町村の景観ガイドラインや、不動産管理会社の規定を確認しておきましょう。
特に以下のようなエリアでは要注意です:
- 歴史的景観を重視する地域(例:京都、鎌倉など)
- 景観条例が厳しい住宅街や観光エリア
- 建物の管理規約により看板設置が不可な場合も
(出典: 国土交通省)
近隣住民とのトラブル防止策
車の出入りや看板、夜間営業などが原因で近隣とトラブルになることもあります。
事前に取るべき対策としては:
- 駐車スペースの確保・整備(車の出入り音や停車位置に配慮)
- 看板の光量や位置に配慮
- ゴミの分別・搬出方法を管理会社と調整
- 開業前に地域挨拶やチラシ投函で誠意を見せる
よくある質問(Q&A)
Q1:駅前じゃないと集客できないの?
- 住宅街やロードサイドでも成功している事例は多数あります!
- 駅前は人通りが多く、認知されやすいという大きなメリットがありますが、それだけが接骨院経営の成功要因ではありません。実際には、駅から離れた住宅街で開業し、地域密着型の運営によってリピーターをしっかり獲得しているケースもあります。
- また、郊外のロードサイドに立地し、駐車場を完備することで車で通いやすくし、家族連れの来院を促している接骨院もあります。さらに、高齢者が多いエリアでは送迎サービスを取り入れることで通院のハードルを下げ、安定した集客につなげている事例も見られます。
- 大切なのは、「ターゲットにとって通いやすい立地かどうか」、そして「その立地に適した集客戦略を立てられるかどうか」という視点です。駅前以外でも、戦略次第で十分に成功できる可能性があるのです。
Q2:開業エリアはどうやって絞る?
- ターゲット×生活動線を基に3〜5件比較すべきです。
- 開業エリアを選ぶ際に重要なのは、“人通りの多さ”ではなく、“自院のターゲット層の患者さんが日常的に通る場所かどうか”という視点です。
- たとえば、高齢者、学生、会社員など、来てほしい層をまず明確にし、その人たちがどのような生活動線を持っているかをリサーチします。通勤・通学ルートや買い物の頻度が高い場所などを把握した上で、条件に合致しそうなエリアを3〜5か所ピックアップし、実際に現地を訪れて調査しましょう。
- 現地では、通行量の多さや駐車場の有無、競合院の数とその質などを確認し、数値や目視で比較することが大切です。「なんとなく良さそう」といった感覚的な判断ではなく、データと行動に基づいて判断することで、開業後の安定経営につながります。
まとめ|接骨院の開業立地に関するまとめ
接骨院の開業において、立地選びは成功のカギを握る最重要ポイントです。ただ人通りが多い、駅に近いといった理由だけで選ぶと、思わぬコストや集客の壁に直面することもあります。大切なのは、ターゲットに合った生活動線上にあるかどうか、家賃や競合状況が経営に見合っているか、そして行政や地域の制約をクリアしているかという視点です。この記事で紹介したステップや事例を参考に、自院に最適な立地を冷静に見極め、後悔のない開業を実現しましょう。
接骨院の経営管理にお困りの方へ
「日計票クラウド」は接骨院向けの顧客管理システムで、簡単に経営分析や患者さんの離脱防止が可能です。紙の日計票の内容を入力するだけで、自動で売上や離脱リスクを可視化や、LINEでのリマインドが可能です。クラウド型でどこからでもアクセスでき、シンプルな操作性に加え、Excelやアプリのインストールも不要です。初期費用なしでご利用いただけるプランもご用意しています。
関連する記事
接骨院開業に役立つブログの活用法とは?集客・経営に効く情報発信のポイント
接骨院を開業したばかりで集客に悩んでいませんか?そんな時こそ効果を発揮するのが「ブログ」です。広告費をかけずに新規患者さんの数がアップした実例もあるように、ブログは開業初期の強い味方となるでしょう。この記事では、すぐに実践できるブログ集客術…
接骨院の顧客管理を強化する方法|収益を最大化する戦略と成功事例
この記事は、患者さんの管理を活用して収益を高めたい接骨院経営者の方に向けた内容です。「施術はしているのに利益が伸びない」「患者さんの管理が煩雑で追いつかない」と感じている方は少なくありません。その原因の多くは、患者さんの管理の仕組みが整って…
リラクゼーションサロンの売上と年収は?開業成功のポイントも解説!
「リラクゼーションサロンを開業したけれど、思ったより売上が伸びない…」そんな悩みを抱えている方は少なくないのではないでしょうか。この記事では、実際の売上データや、よくある課題の改善策、そして黒字化・安定経営を実現するためのヒントを詳しく解説…
リラクゼーションサロンを開業するには?必要な準備・費用・失敗しないコツを徹底解説!
リラクゼーションサロンの開業は、やりがいのある仕事である一方、事前の準備や知識がないと「思ったより大変だった…」と感じてしまうことも。この記事では、リラクゼーションサロンを開業するために必要な準備・費用・ステップをはじめ、失敗を防ぐためのポ…
接骨院の開業資金と売上の目安|自己資金・調達方法・黒字化のコツまで解説
「接骨院を開業したいけれど、いったいどれくらいの資金が必要なのだろうか?」そんな疑問を抱えている方に向けて、この記事では開業にかかる初期費用や運転資金の目安から、自己資金の準備方法、融資や補助金の活用、黒字化のシミュレーションまで、開業準備…
接骨院の年収は本当に儲かるのか?|成功のための戦略と実際の収益
国家資格を活かして働ける柔道整復師は、接骨院をはじめ、スポーツ現場や介護施設など幅広いフィールドで活躍できる専門職です。しかし「年収は実際どれくらい?」「開業したら儲かるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。この記事では、勤…