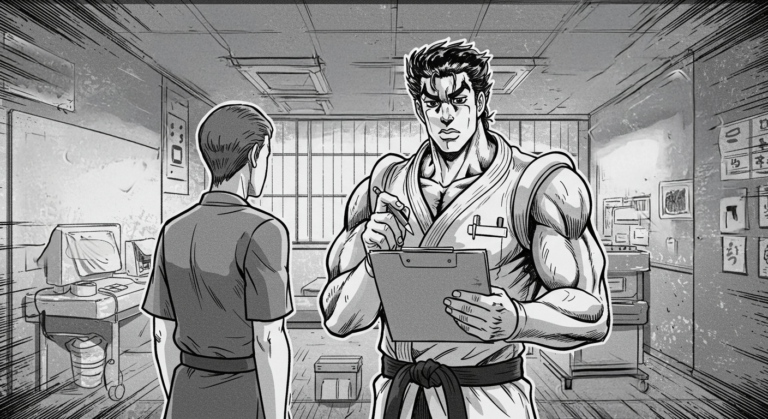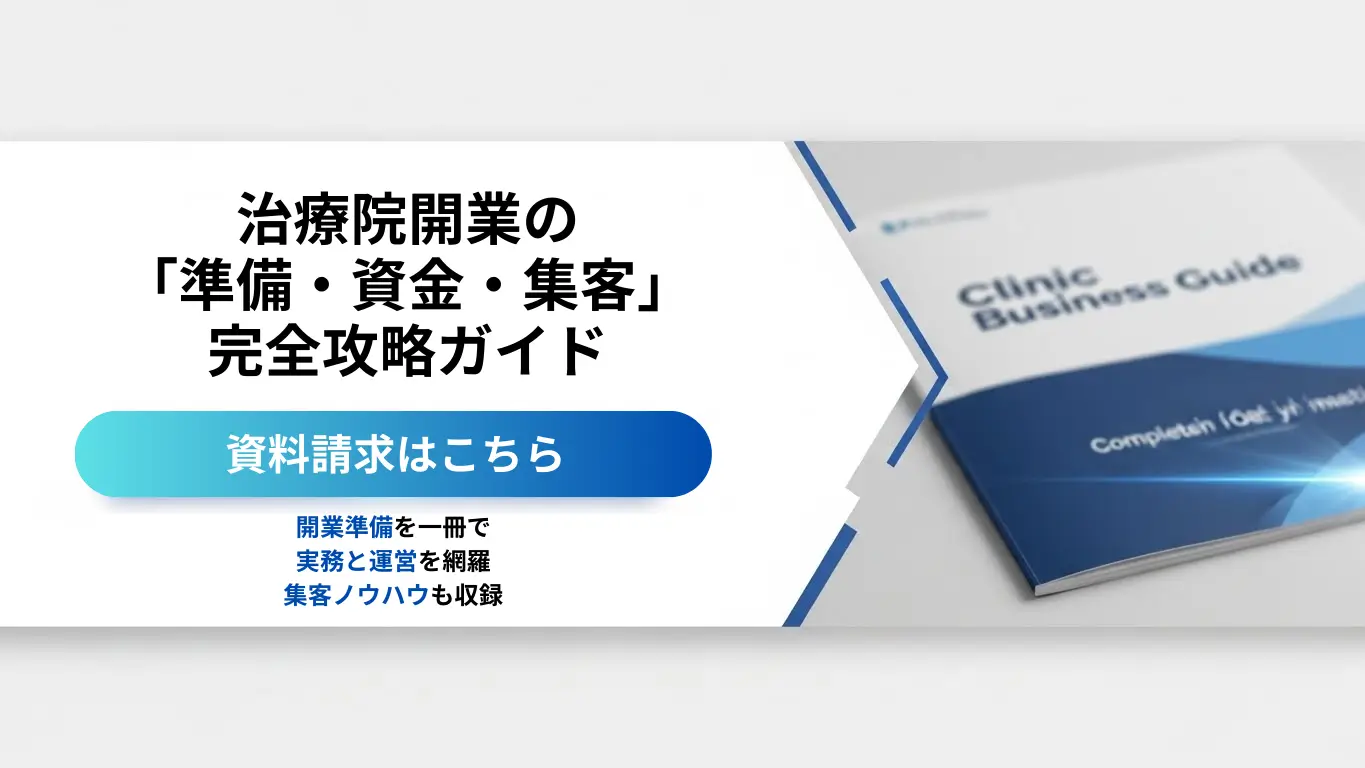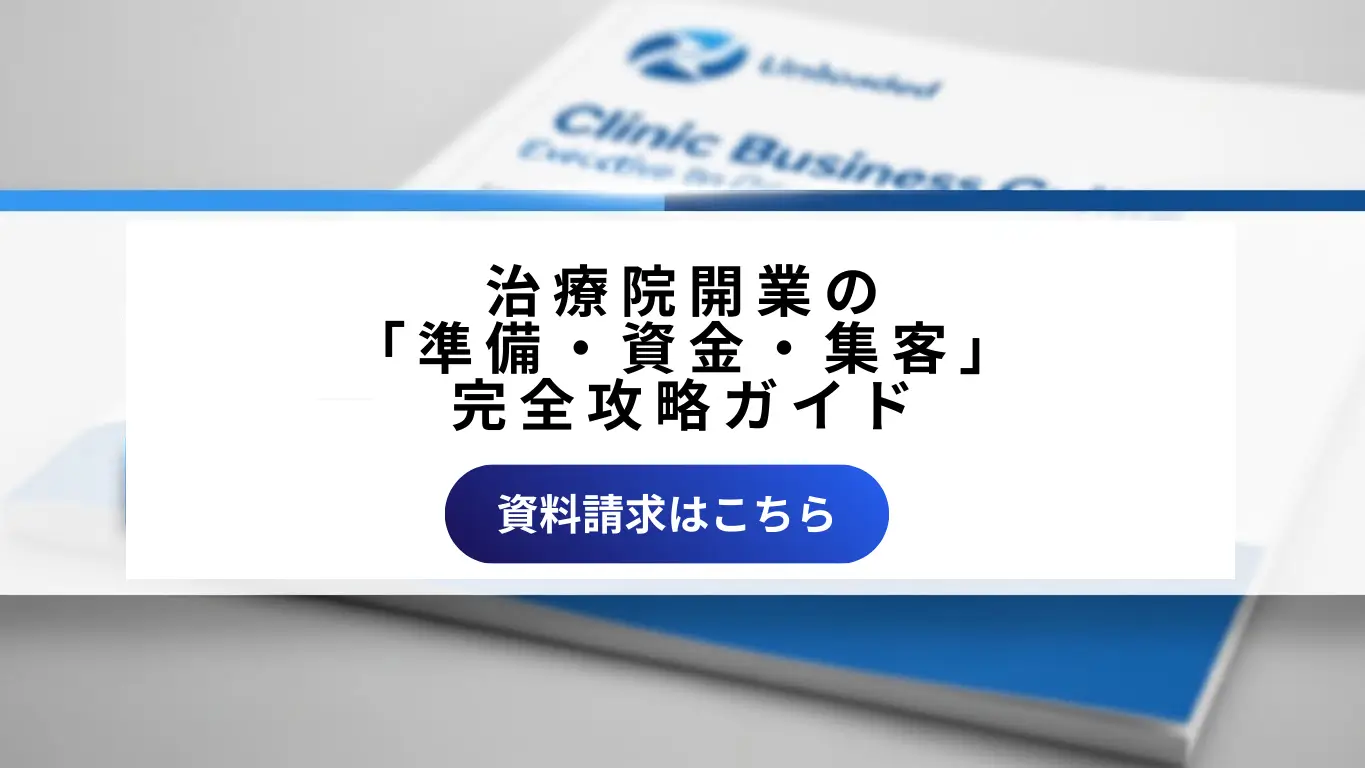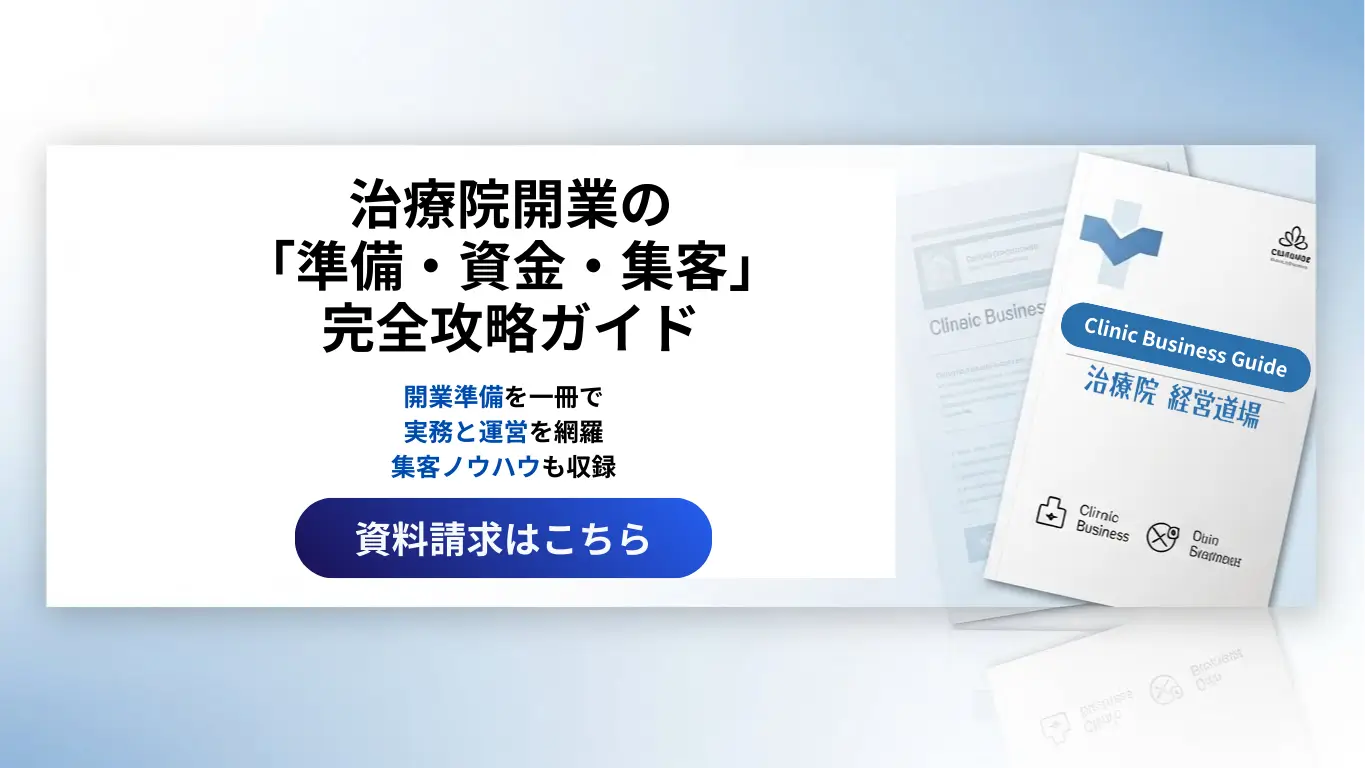接骨院を経営する上で、保険を適用した施術は患者にとって利用しやすい環境を整えるために重要な要素です。しかし、保険の適用には一定のルールがあり、適切に運用しなければトラブルに発展する可能性もあります。この記事では、接骨院の施術者や経営者向けに、保険適用の基本ルールや必要な手続き、料金設定のポイント、トラブルを防ぐための対策について詳しく解説します。
▼関連記事▼
・整体院コンサルで集客力アップ!成功するための戦略とポイント
・治療院集客の成功法則!患者を引き寄せるための効果的な施策とは
・理学療法士が整体院を開業するためのステップと成功のポイント
・接骨院イベントの企画・運営ガイド:集客と患者さん満足度向上を実現する方法
目次
接骨院の保険適用について知っておくべき基本事項
接骨院を運営する上で、健康保険の適用について正しく理解することは非常に重要です。不適切な請求は、患者とのトラブルや健康保険組合からの指導対象となる可能性があるため、以下の基本事項をしっかり押さえておきましょう。
1. 保険適用の対象となる症状
接骨院で健康保険が適用されるのは、外傷性の負傷に限られます。具体的には以下のようなケースです。
- 骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)
- 打撲・捻挫(いわゆる「肉離れ」なども含む)
- 挫傷(筋肉や軟部組織の損傷)
また、慢性的な肩こりや腰痛、疲労回復目的の施術には健康保険は適用されません。
慢性疾患に対する施術を保険で請求することは不正請求とみなされるため、注意が必要です。
(出典: 森永健康保険組合)
2. 保険請求時の必要書類
適正に保険請求を行うためには、以下の書類をしっかりと準備し、正確に記入することが求められます。
- 療養費支給申請書(レセプト)
- 施術録(カルテ)
- 負傷原因を記載した問診票
特に、負傷原因の記載が不明瞭だと、健康保険組合からの照会や返戻のリスクが高まります。「いつ」「どこで」「どのように」負傷したのかを明確に記録しましょう。
3. 療養費支給申請のポイント
保険請求の際に注意すべきポイントを押さえておきましょう。
① 負傷原因の明確化
「〇月〇日、階段を踏み外して右足首を捻った」など、具体的な負傷状況を記載することが重要です。「いつの間にか痛くなった」「慢性的に痛む」などの記載では保険適用外となります。
② 他の医療機関との重複請求に注意
患者が同じ負傷で病院や整形外科に通院している場合、重複請求は不可です。重複請求は、監査対象となるため、事前に確認が必要です。
(出典: 厚生労働省)
③ 継続施術の適正管理
急性期の外傷であれば、通常は数週間から長くても2~3か月で回復するケースが多くみられます。長期間にわたる保険施術の継続は、健康保険組合から疑義照会が入る可能性が高まるため注意が必要となるかもしれません。
4. 不正請求を避けるための注意点
接骨院の保険請求に関する監査は年々厳しくなっており、不適切な請求は指導が行われることや、場合によっては行政処分の対象となります。万が一、健康保険組合から照会があった場合は、正確な施術録と問診票を提示できるように準備しておくことが大切でしょう。
- 架空請求(実際には施術していないのに請求する)
- 水増し請求(本来の回数や部位数より多く請求する)
- 慢性的な症状への不適切な保険適用
5. 保険外施術とのバランス
健康保険の適用範囲には限りがあるため、自費施術(保険外施術)とのバランスを取ることが経営上重要なポイントです。適切に保険請求を行いながら、自費施術のメニューを充実させることで、安定した経営基盤を築くことができるかもしれません。
- 保険施術:外傷の急性期施術(短期間)
- 自費施術:慢性痛、リラクゼーション、骨盤矯正、姿勢改善など
接骨院の保険適用についてのまとめ
接骨院の保険適用については、以下の点をしっかり押さえておきましょう。正しく保険を活用し、患者にも信頼される接骨院経営を目指しましょう!
- 健康保険が適用されるのは急性外傷のみ(慢性疾患は不可)
- 適正な書類管理(レセプト・施術録・問診票の徹底
- 負傷原因を明確にし、過剰請求・重複請求を避ける
- 長期間の保険施術には注意し、必要に応じて自費施術を活用
接骨院での保険適用を受ける際の必要書類と手続き
接骨院を運営する上で、健康保険の適用手続きは重要な業務の一つです。適切な手続きを踏まないと、患者の保険請求が通らず、トラブルに発展する可能性もあります。下記では、保険適用を受ける際の必要書類と手続きの流れを詳しく解説します。
1. 健康保険が適用される範囲
健康保険が適用されるケース
- 以下のような「外傷性がある負傷」が対象です
- 骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)
- 打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
- 急性・亜急性の外傷(原因がはっきりしているもの)
健康保険が適用されないケース
- 慢性的な肩こり・腰痛
- 疲労回復やリラクゼーション目的の施術
- 交通事故(自賠責保険対象)や労災事故(労災保険対象)
2. 保険請求に必要な書類
保険適用を受けるためには、適切な書類の準備が必要です。以下の書類を準備しましょう。また、レセプトの記入ミスがあると、支給遅延や不支給の原因となるので細心の注意を払いましょう。
(出典: 全国統合医療協会)
① 療養費支給申請書(レセプト)
健康保険組合(健康保険組合や協会けんぽ等)へ提出する書類で、毎月締めて請求します。
- 患者情報(氏名・生年月日・健康保険組合など)
- 負傷日・負傷原因
- 施術内容・施術部位
- 施術費用
② 受領委任の同意書
接骨院が患者の代わりに保険請求を行う場合、患者の同意が必要です。
- 初回の来院時に署名・捺印をもらう
- 一度取得すれば継続して使用可能
③ 負傷原因の説明書
負傷の原因・日時・状況を明確に記載し、「日常生活で発生したケガ」であることを証明します。曖昧な記載は健康保険組合からの照会(問い合わせ)が増える原因になるので注意しましょう。
- 例:「階段を踏み外して右足首を捻挫」
- NG例:「仕事中に重い荷物を持ち上げて痛めた」➡ 労災対象
④ 施術録(カルテ)
施術の記録をしっかり残しておくことで、健康保険組合からの問い合わせ対応がスムーズになります。
- 負傷状況と経過(施術の進捗)
- 施術内容(電気施術・手技・固定など)
- 再発防止指導の有無
3. 保険請求の流れ
ステップ①:初診時の対応
- 健康保険証の確認(保険適用範囲かどうかを判断)
- 受領委任の同意書への署名
- 負傷原因の確認・記録
ステップ②:施術の実施・記録
- 施術内容の記録(カルテ作成)
- 患者ごとの施術費用を管理
ステップ③:月末のレセプト作成・提出
- 療養費支給申請書(レセプト)を作成
- 健康保険組合へ請求(レセプトオンライン請求または紙請求)
- 健康保険組合からの照会対応(必要に応じて)
ステップ④:健康保険組合からの支払い
- 2~3ヶ月後に療養費が振り込まれる
- 支給されない場合、記載ミスや確認不足の可能性がある
4. 注意点とよくあるトラブル
- 不正請求は絶対NG!
「慢性痛への施術」「水増し請求」など、不正が発覚すると最悪の場合、保険請求停止や返還請求の対象になります。 - 照会(問い合わせ)に対応できる準備を
健康保険組合から「負傷原因」や「施術の正当性」について問い合わせが来ることがあります。適切な記録を残しておくことで、スムーズに回答できます。 - 患者への説明を丁寧に
「接骨院の施術は全て保険が効く」と誤解している患者も多いです。適用範囲や自己負担額について、事前にしっかり説明しましょう。
接骨院における保険診療の際の注意点とトラブル回避方法
1. 保険適用の範囲を正しく理解する
接骨院での健康保険適用は、以下の外傷性が明確な急性・亜急性疾患に限定されます。誤った保険請求は指導・監査の対象となるため、施術前にしっかり確認することが重要です。
- 保険適用となるケース
- 骨折・脱臼(応急処置以外は医師の同意が必要)
- 捻挫・打撲・挫傷(筋・腱の損傷を含む)
- 保険適用外となるケース
- 慢性的な肩こりや腰痛
- 疲労回復を目的とした施術
- 神経痛やリウマチなどの内科的疾患
- 仕事や家事による単なる筋肉疲労
2. カルテ・施術録の適正管理
カルテ(施術録)の不備は、監査時の指導対象になることが多いため、以下のポイントを押さえましょう。また、負傷原因の記載漏れは、特に監査で問題視されやすいため、「原因不明」などの曖昧な記述は避けましょう。
- 施術録に記載すべき内容
- 負傷原因(いつ・どこで・何をしているときに負傷したか)
- 症状の詳細(どの部位がどの程度痛むか、腫れや可動域制限の有無)
- 施術内容(電療・手技療法の種類と時間)
- 経過・改善状況(前回施術との比較、効果の有無)
3. 患者説明と同意の徹底
患者に対して、保険適用の範囲や自己負担額についてしっかり説明し、同意を得ることが大切です。 患者の署名を必ずもらい、同意書や説明書の控えを残しておくことで、後のトラブルを防ぎましょう。
- 説明すべきポイント
- 保険が適用される条件と範囲
- 施術費の負担割合と自己負担額
- 併用療養の有無(自費施術との組み合わせ)
- 療養費の償還払いの流れ(必要な場合)
4. 不正請求をしない(指導・監査の対象を避ける)
不正請求は、接骨院の信用を失うだけでなく、返還請求や行政処分のリスクがあります。毎月の請求内容を定期的にチェックし、不備がないか確認する習慣をつけることが重要です。
- よくある不正請求の例
- 架空請求(実際に施術していないのに請求)
- 水増し請求(実際より回数や部位を増やして請求)
- 慢性疾患への適用(保険対象外なのに適用)
- 二重請求(他院と重複して請求)
5. 監査・指導に備える
保険請求をしている以上、行政の監査や指導を受ける可能性はゼロではありません。以下の対策を行い、いつ指導が入っても問題ないように準備しておきましょう。
- 監査対策のポイント
- 施術録を適切に管理し、最低5年間は保管する
- 患者説明・同意の記録を確実に残す
- 請求内容を定期的に見直し、不正がないかチェックする
- 指導を受けた場合は速やかに改善し、再発防止策を講じる
接骨院で保険適用を行う場合の料金設定と患者への説明方法
1. 接骨院で保険適用できるケースと料金設定
健康保険が適用されるのは、「外傷性の負傷(骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷)」に限られます。慢性的な肩こりや腰痛、疲労回復を目的とした施術は保険適用外となります。
(1) 保険適用時の料金目安
保険診療の料金は、厚生労働省の定める基準に基づいています。以下は一般的な自己負担額の目安です。※金額は地域や加算要素(初検料・再検料など)によって変動するため、詳細は各自治体の基準を確認してください。
| 負傷部位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 1部位 | 約200円 | 約400円 | 約600円 |
| 2部位 | 約300円 | 約600円 | 約900円 |
| 3部位 | 約400円 | 約800円 | 約1,200円 |
(出典: 全国柔道整復師会)
(出典: 厚生労働省)
(2) 保険適用外となるケース
接骨院経営者は、下記のルールを理解し、不正請求を防ぐことが重要です。
- 慢性疾患(肩こり・腰痛・神経痛など)
- 疲労回復・リラクゼーション目的の施術
- 病院との併用(整形外科で同じ部位の施術を受けている場合)
- 負傷原因が不明確なもの
2. 患者への適切な説明方法
(1) 受付時の説明ポイント
- 「いつ・どこで・どのように」負傷したかを確認
- 例:「◯月◯日、階段を踏み外して足首をひねった」→ 保険適用
- 「何となく痛くなった」→ 保険適用外(自費診療)
- 保険適用の条件をわかりやすく伝える
- 「健康保険が使えるのは、急なケガ(捻挫・打撲など)の場合です。」
- 「肩こりや慢性的な腰痛は保険の対象外です。」
- 自己負担額と施術内容の説明
- 「本日は健康保険適用で◯円になります。追加で自由施術を希望される場合は、+◯円です。」
(2) 書類記入時の対応
保険請求には負傷原因の明記が必須です。患者に「原因が必要」と伝え、正確に記入してもらいましょう。
NG例:「なんとなく痛い」 → 不明確で審査が通らない可能性
OK例:「◯月◯日、スポーツ中に足をひねった」
3. 自費診療との組み合わせ方
保険適用が難しい場合でも、患者の症状に合った自費施術メニューを提案することで、満足度を高められるでしょう。
(1) 自費メニューの提案例
- 保険適用内の施術+自費施術
- 例:「基本の保険施術に加え、より効果を高めるために+〇〇円で特別ケアを受けられます。」
- 完全自費メニュー(慢性疾患向け)
- 例:「慢性的な腰痛は保険適用外ですが、〇〇円で専門的な施術が可能です。」
(2) 患者に納得してもらうための説明方法
- 「健康保険は急なケガに適用されるものなので、慢性的な痛みには適用できません。ただ、〇〇という自費メニューでしっかりケアできます。」
- 「一度の施術では治りきらないので、定期的なケアをおすすめします。」
4. 保険適用のルールを守る重要性
不正請求や誤った保険適用は、行政指導や返還請求のリスクがあります。
- カルテ・施術録をしっかり記録する
- 患者に正しい情報を伝える
- 無理に保険適用しない(グレーゾーンを避ける)
接骨院の保険に関するまとめ
接骨院での保険適用は、骨折・脱臼(医師の同意が必要)、打撲・捻挫・挫傷などの外傷性の負傷に限られるため、患者に事前説明を徹底することが重要です。適切な書類作成と正確な保険請求を行い、不正請求を防ぎましょう。また、保険施術と自費施術の違いを明確にし、料金を分かりやすく説明することでトラブルを回避できます。適正な運用により、患者の負担軽減と接骨院の信頼向上につなげましょう。
接骨院の経営管理にお困りの方へ
「日計票クラウド」は接骨院向けの顧客管理システムで、簡単に経営分析や患者さんの離脱防止が可能です。紙の日計票の内容を入力するだけで、自動で売上や離脱リスクを可視化や、LINEでのリマインドが可能です。クラウド型でどこからでもアクセスでき、シンプルな操作性に加え、Excelやアプリのインストールも不要です。初期費用なしでご利用いただけるプランもご用意しています。
関連する記事
鍼灸院の集客完全ガイド|オンライン×オフラインで成果を出す6つの戦略
鍼灸院の集客は、競合の増加やターゲット層の変化により難易度が高まっています。口コミや価格競争だけに頼るのではなく、オンラインとオフラインを組み合わせた戦略が欠かせません。この記事では、明日から実践できる6つの集客施策を分かりやすく解説します…
【2026年版】整骨院の自費施術の料金相場は?全国の整骨院の実際のトレンドを分析&解説
「整骨院の自費施術、うちは高いのか安いのか…?」 そんな疑問を抱えたまま料金設定をしていませんか?近年では、整骨院でも保険施術に加えて「自費メニューを導入する動き」が広がっています。 その一方で、下記のように悩む経営者の方も少なくありませ…
接骨院イベントの企画・運営ガイド:集客と患者さん満足度向上を実現する方法
「もっと地域の方に知ってもらいたい」「患者さんとの信頼関係を深めたい」_そんな想いから、接骨院でのイベント開催を検討する経営者の方も増えています。 実は、イベントはただの集客手段ではなく、患者さん満足度の向上や口コミによる広がりにもつながる…
リラクゼーションサロン開業資金の準備ガイド:必要額や資金調達方法
接骨院を経営されている方の中には、「リラクゼーションサロンを開業したいけれど、資金はいくら必要?」「どうやって準備すればいいの?」 そんな疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか。サロンの規模や場所によって必要な金額は異なりますが…
リラクゼーションサロン開業届の手続きと注意点【必要書類・申請方法を徹底解説】
リラクゼーションサロンを開業する際、忘れてはならないのが「開業届」の提出です。 開業届は事業をスタートする上での第一歩であり、税務上の大切な手続きでもあります。しかし、「どこに提出すればいいの?」「必要な書類は何?」「個人事業主として何か注…
治療院の集客を加速させるホームページ活用法とは?効果的な施策を徹底解説
「もっと患者さんに来てほしい…」 そんな悩みを抱える治療院の経営者の方にとって、ホームページは集客を加速させる強力な武器になります。 今や、インターネットでの情報収集は当たり前。どれだけ腕の良い施術でも、その魅力が伝わらなければ来院にはつな…